『第百回目の探勝会』
武蔵野探勝は、足かけ10年にわたり原則として毎月第一日曜日に行われてきた。その第100回目、すなわち一番最後の昭和14年1月の第一日曜日が1日、元日であった。
昭和18年2月15日発行『武蔵野探勝』甲鳥書林版も、昭和44年11月20日発行有峰新社版も、『鶴ヶ岡八幡宮初詣』という表題で、昭和14年1月1日の開催とされている。しかし、実際に吟行が行われたのは、実は1月8日のことであった。
この点について、高濱虚子はこう記している。
『武蔵野探勝は丁度今回で百回に達するので、それを記念する為め粗餐でも差上げたいと思つたところであるから両方を合併して催したいものという考へがあつたのであつたが、元旦はそれを合併して催すほど多人数を入れる場所で空いてゐるのが鎌倉には無かつたので、止むを得ず第二日曜の八日に延期して、海浜院で催すことになつた。』
このときの句会場になった海浜院は、現在の由比ガ浜4丁目6ー1に所在していたホテルであるが、残念ながら現存していない。この武蔵野探勝から7年後の昭和21年1月に米兵の火の不始末により焼失してしまった。
武蔵野探勝が行われた昭和14年当時は、鎌倉海浜ホテルとして営業していたが、虚子は『海浜院』と記載している。これは、同ホテルの前身が明治20年に海水浴を取り入れたサナトリウム「保養所海浜院」だったことによる。虚子の吟行当時は、木造二階建て、室数54の海岸を見下ろす堂々たるホテルであった。
虚子は記す。
『一番に草庵に訪れたのは高野素十君で吹雪の新潟から出て来て、(略)つづいて見えたのが和歌山の松岡春泥、芙蓉の夫妻、大阪の大橋桜坡子君であつた。其うちに真下夫妻、たけし、夢香、今井夫妻、友次郎夫妻等がだんだん集つて来て前々日より来て居た年尾』
『昼食が済んだ時分にその霰も小止みになつたので、折節玄関に来た莉花女、沼蘋女、らく女さん等も一緒になつて一同で先づ鶴ヶ岡八幡宮に初詣した』
昭和3年当時の海浜ホテルにあった電車時刻表によると、10時に東京を発つと新橋10時5分、横浜10時37分、鎌倉11時11分となっている。女性陣三人はこの電車で来たのかもしれない。ちなみに、現在のダイヤでは東京発10時1分発で鎌倉着は11時1分であり、わずか10分の違いでしかない。現代の我々は、昭和初期の鉄道を決して侮れない。
虚子は記す。
『太鼓橋のほとりで先づ奈王君に出くはした。それから舞殿のほとりに行くと多くの人々が手帳に句を書留めてゐるのに出逢つた。(略)石段を登つて社殿の前に立つと、そこにも手帳に句を認めてゐる沢山の人が居た。』
この探勝会では55人もの参加者が確認できている。なお、故山本柊花同人会長のお父上である山本薊花(けいか)氏も参加しており、「松古りて鎌倉山の寒鴉」「沖つ波荒れ冬空は低く垂れ」という句が虚子に採られている。この二句は、句集「続 白珠」に収められている。
さて、海浜ホテルの情景はどのようなものであったろうか。
虚子は記す。
『海浜院にはクリスマスツリーもしてあれば餅花もしてあつた。(略)ホールには西洋人の団体も居り普通の客も居るのであつて、其等が入交じつて休憩しているのはどことなく春めいた感じであつた。
馬車駆りてホテルの句会と鳥総松 日ねもす
スチーム温くしコリント遊び子等はする 湘海
暖炉の火ほのぼのと靴に絨毯に 清三郎
餅花は静かラヂオは絶間なく たけし』
湘海の句に出てくる『コリント遊び』とは、スマートボールの原型とも言うべきもので、パチンコ台を横に寝かせた形をしている。
『食堂の用意が出来たといふ知らせがあつたので今度は食堂に変つてをるさきの披講の場所に入つてテーブルに著いた。それから私は「御機嫌よう」と言つて盃を挙げたら、水竹居氏は「万歳」と言つて盃を挙げた。一同はそれに和した。御馳走は洵に粗末なものであつたけれど、これで武蔵野探勝の百回を記念し祝福したことになり、私は満足を覚えたのであつた。』
どのような食事だったのかについて、虚子が全く触れていないのは少し残念である。
それはさておき、第一回の昭和5年8月27日、府中の大国魂神社裏の安養寺で始まった武蔵野探勝が百回を数え、海浜ホテルの食堂にて幕を閉じた。その後のことについて、虚子はこう書いている。
『「日本探勝」と名を改め、二月から出来る限り地方の俳句会とも連絡を取り、広く日本の探勝に乗り出すことにしようと思ふ。(略)そこで其第一回に当たる二月の探勝会は尾張、三河地方の俳人諸君と共に二月十一日(紀元節)十二日(日曜)蒲郡で催して見ようかと考へて居り、目下交渉中である』
一つの偉大なる吟行会の終わりは、すなわち次の吟行会のスタートでもあった。虚子の俳句探勝はまだまだ続くのである。

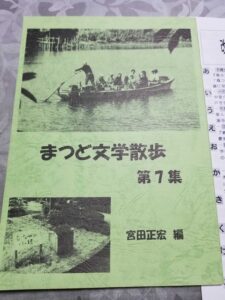 第6集までの「まつど文学散歩 総集編」は、非常に貴重な著書で、「2011.3.3」の日付で、サインをしていただいたことを昨日のことように覚えています。
第6集までの「まつど文学散歩 総集編」は、非常に貴重な著書で、「2011.3.3」の日付で、サインをしていただいたことを昨日のことように覚えています。 「斜陽」には、『あのあたりは梅の名所で、冬暖かく夏涼しく(略)、十畳間と六畳間と、それから支那式の応接間と、それからお玄関が三畳、お風呂場のところにも三畳がついていて、それから食堂とお勝手と、それからお二階に大きいベッドの附いた来客用の洋間が一間』という描写がなされている。
「斜陽」には、『あのあたりは梅の名所で、冬暖かく夏涼しく(略)、十畳間と六畳間と、それから支那式の応接間と、それからお玄関が三畳、お風呂場のところにも三畳がついていて、それから食堂とお勝手と、それからお二階に大きいベッドの附いた来客用の洋間が一間』という描写がなされている。 曾路は、ぽんと手を打つと矢立を取り出して何やら書き始めた。
曾路は、ぽんと手を打つと矢立を取り出して何やら書き始めた。