一、はじめに
虚子とその一門は、昭和五年八月から月一度の吟行を行い、それを「武蔵野探勝」と称した。この吟行会は昭和十四年まで続けられ、その回数はちょうど百を数えた。
武蔵野探勝第六十四回は、昭和十年十一月三日にハンセン病療養所である全生病院で行なわれている。
当時、療養所には「ホトトギス」投句者を中心とした入所者による俳句愛好会『芽生会』が活動しており、俳誌『芽生』八十四号(昭和十年十二月一日発行)は武蔵野探勝会歓迎号とされている。この俳誌の存在によって、探勝会参加者全員を特定することができる。
また、現在は『国立療養所多磨全生園』となった当地には国立ハンセン病資料館が併設されており、その図書室には『芽生』以外にも『山桜』『愛生』『楓』など虚子に関係する貴重な俳誌も保管されている。
二、第六十四回『全生病院』中村汀女、高木晴子、星野立子記
この回は、女流三人による会話形式の記録となっている。
『―新宿から村山までのドライブは素的でしたね。(略)
―病院の芝生はきれいでしたね。松があって。
―赤松でしたね。』
このような会話で話は進んでいく。現在の全生園も正門から療養所入り口付近には立派な赤松がある。
『―先づ軍隊式の大きな炊事場が目に残りましたね。井戸端に二人の患者さんが菜っ葉を洗ってゐましたっけ。』
炊事場、井戸端は現在の給食棟、洗濯場の付近にあった。『―菊を作ってゐる籬に沿うて左に折れて行くと、ミシンをかけたりしてゐた一軒が目につきましたがそれは百合舎といふ名の女の人ばかりの住んでゐる家でした。(略)
―少年寮の人達は、大変大さわぎして遊んでゐたのに、私達が通る時、バタンと戸を閉めてしまひました。』
園内には当然子どもたちもいた。彼ら彼女らは十五歳になるまで少年寮、少女寮に住むことになっていた。少年寮は「若竹舎」「桐舎」、少女寮は「百合舎」「椿舎」と言う名称だった。
『―広場もあって、そこの傍に全生富士といふお山がありました。』
これは大正十四、五年の敷地拡張時に入所者の希望により入所者たちの手で造った築山で、現在は「望郷の丘」と呼ばれている。
『―広場から正面に講堂が見えてゐましたね。杖をたよりに二三人歩いてゐた人がその講堂に上ってゆくのに気がついてふと中を見ると、演壇に立って話しをしてゐる父が見えました。』(略)
『―先生のお話、遅れて行ったので半分きりきけませんでした。
―山本暁雨さんの答辞に胸がいっぱいになりました。「刻々に蝕まれゆくばかりの・・・」と声もしっかりと立ちつづけて話される姿に泣かされました。』
ここでいう講堂は、「礼拝堂」であり、現在の厚生会館付近にあったと思われる。
この時の虚子の五分ほどの挨拶は前出の『芽生』に筆記録が残っている。
残念ながら暁雨の答辞は残されていないが、『芽生』には答辞内容が推察できる文章が掲載されている。
三、虚子と暁雨の挨拶(抜粋)
虚子
『此の四季の現象を最もよく受け入れて楽しみ且つ詠ずるのは、俳句を作る人の特権であります。俳句を作られる方は、実に此の天が与へてくれた幸福を受け入れる権利を所有し行使する方であると思ふ。今を時めく人でも四季自然の移り変りに全く無関心で此の天与の幸福を享受し得ないのに比して、あなた方が、それに深い関心を持ち俳句を詠ぜられると云ふことは大へんな幸福であると私は思ひます。
「ホトトギス」にも皆さんの投句が多くあります。それを見てゐるといつでも私は考へます。(略)成績の如何を問はずして、只四季の移り変りを純粋に楽しむこと、そのことが非常に幸福であります。成績に囚はれ成績を気にすることは、折角の幸福を不幸にして了ひます。そうしたことを問題にせず、皆さんは唯純粋に、俳句に遊ぶといふ考へさへあれば、非常な幸福であると考へます。』
『栄えの日に逢ひて』山本暁雨
『月々ホトトギスに投句する事を許されて、一般作者と何等分け隔てなく、懇切叮嚀なる御指導を給はってをる事だけでも、私共にとって過分の事と、芸術の有難さを痛感しをる次第である。
凡そホトトギスの流れを汲む句会は、全国津々浦々到る所に散在し、まだ見ぬ虚子先生を慕ひ憧れてゐる多くの作者のことを思ふ。然れども健康と自由に恵まれてゐる其人々は、仮令何なる僻地に住むと雖も、何時かは先生の臨まるる句会に或は講演会に逢ひ得らるる可能性があるのである、が併し私共の如き隔離療養を受けてゐる者に至っては、レコードに依るか或は又マイクを通して先生の御声を拝聴する外道はないのである。況して先生の臨まるる句会など出る、といふやうな事は夢以外には許されぬ儚い望みであった。然るに何たる幸福ぞ、突如として、虚子先生を中心とせらるる、武蔵野探勝会の御一行がわが村を訪れらるる、の吉報が齎らされたのである。(略)
虚子先生が私共に給はった御言葉こそ、斯道修行の標識灯となり、芽生俳壇の行く手は光り輝き大いなる希望に満たされたのである。(略)』
四、おわりに
現在、全生園のような国立ハンセン病療養所は全国に十五ほどある。
平成三年十一月三日に紫綬褒章を受章された俳人・村越化石(濱)は草津町の栗生楽泉園に入所されていた。
家族からも一般社会からも完全に隔離された入所者たちは何を思っただろうか。
「誰からも必要とされていない」という絶望の中から、それでも彼らは創作という一つの道を見出し、閉ざされた一角の中で懸命に生きてきた。国立ハンセン病資料館にはそうした入所者たちの声がぎっしりと詰まっていた。
人々からとうに忘れられた武蔵野の雑木林の一角にある療養所を虚子が訪ねていたことに心から敬意を表したい。 そして、中学・高校時代にすぐ隣の小平市に住んでいながら、その存在をまったく知らなかった私は、このたび多磨全生園に訪問できたことを心から喜んでいる。

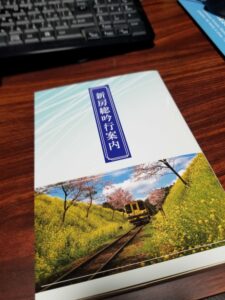 俳人協会から4月に発刊された『新房総吟行案内』が届きました。
俳人協会から4月に発刊された『新房総吟行案内』が届きました。 新興美術院「新興展」が開催されている東京都美術館に行ってきました。
新興美術院「新興展」が開催されている東京都美術館に行ってきました。 『堤から岐れ下りた道の所に二本の柱だけの門があり、簡単な小舎が建つてゐるだけで、あとは点々と草の萌え出た、唯広い許りの運動場が雨を受けてゐた。』
『堤から岐れ下りた道の所に二本の柱だけの門があり、簡単な小舎が建つてゐるだけで、あとは点々と草の萌え出た、唯広い許りの運動場が雨を受けてゐた。』 さて、こうして第五十六回武蔵野探勝会は近藤邸の雛祭を句材に吟行会が催されたのであるが、水竹居の記録から近藤邸のたたずまいを見てみよう。
さて、こうして第五十六回武蔵野探勝会は近藤邸の雛祭を句材に吟行会が催されたのであるが、水竹居の記録から近藤邸のたたずまいを見てみよう。 5月21日、千葉県俳句作家協会通常総会に参加しました。
5月21日、千葉県俳句作家協会通常総会に参加しました。 このところ毎日少しずつ「CD整理」に取り掛かっています。
このところ毎日少しずつ「CD整理」に取り掛かっています。 『船橋屋といふ一軒の茶屋があった。其処へ一行は一先づ落付いた。茶屋と云っても海水浴場の憩み場所のやうな、ただ広い掛出しの上に茣蓙を敷いたばかりの処である。一枚の戸障子さへはまってゐない。一面の蘆原を見通して眺めはこの上もない。幸少しの風もない。浴びるやうに日が射し込んでゐる。春のやうに暖かい。』
『船橋屋といふ一軒の茶屋があった。其処へ一行は一先づ落付いた。茶屋と云っても海水浴場の憩み場所のやうな、ただ広い掛出しの上に茣蓙を敷いたばかりの処である。一枚の戸障子さへはまってゐない。一面の蘆原を見通して眺めはこの上もない。幸少しの風もない。浴びるやうに日が射し込んでゐる。春のやうに暖かい。』 今回の吟行は、これまでと異なり東武鉄道からの招待である。観光地として越ケ谷梅林を宣伝し、沿線開発につなげたいということが同社の方針だったとしても、「ホトトギス」誌に掲載されていた「武蔵野探勝」が人気を博してきた証左でもある。
今回の吟行は、これまでと異なり東武鉄道からの招待である。観光地として越ケ谷梅林を宣伝し、沿線開発につなげたいということが同社の方針だったとしても、「ホトトギス」誌に掲載されていた「武蔵野探勝」が人気を博してきた証左でもある。 『今日は流山町あたりで、江戸川べりの寒鮒釣を見ようといふのである、一行十七人、降るかも知れないと懸念した空が晴れて、まアよかつたといふ天気。』
『今日は流山町あたりで、江戸川べりの寒鮒釣を見ようといふのである、一行十七人、降るかも知れないと懸念した空が晴れて、まアよかつたといふ天気。』