1、はじめに
虚子とその一門は、昭和5年8月から月一度の吟行を行い、それを「武蔵野探勝」と称した。この吟行会は昭和14年1月まで続けられ、その回数はちょうど100を数えた。
虚子一行は、昭和6年11月1日の第16回武蔵野探勝会「浦安」で千葉県浦安市を訪れている。
今回は、その日の記録者であった池内たけしの記述を追いながら、当時の吟行の模様を再構成してみたい。
2、「浦安」への経路
たけしは記す。
『十一月一日の第一日曜日午前九時半に深川の高橋に集合することになった。高橋からは浦安行きの汽船が出る。汽船と云っても隅田川の一銭蒸気といづれ劣らぬほどのもので、狭い汚ならしい船室に茣蓙を敷いたばかりの座席と腰掛が並べられてある。私達一行はその座席と腰掛とに割り込んだ。絶えず機械の響きに体が中気病みのやうにブルブル震えた。ガソリンの臭い煙にも苦しめられた。』
当時、高橋から浦安への船便は二つの会社が運航していた。ひとつは、大正八年から東京通船株式会社が就航した定期船で通称「通船」と呼ばれたもの。もう一つは、「通船」の就航後まもなく葛飾汽船会社が出した葛飾丸という十六、七トンほどの小型の定期船である。たけしの記述から、虚子一行は葛飾丸に乗船した可能性が高いことが推察される。
一行の船は『架つている橋の下をくぐつては行く中に稍々水路の広くなった処へ来たと思ったらそれは中川の流れの注いでゐる処』を越え、荒川放水路を越え、江戸川を越える。『この川を渡ると最早東京府ではなくて千葉県に這入るのである。浦安に着く。』
浦安町誌によれば、当時の『汽船発着所は欠真間一六九三番地吉野屋で、同家地先の川岸から乗船する。』とされている。この吉野屋は、現在も猫実五丁目に船宿吉野屋として営業している。
さて、吉野屋にて下船した虚子一行が、現在の境川沿いに河口に向かって歩いたことは間違いない。
以下のような句が詠まれている。
欄干に網と蚊帳とが干されあり 拓水
蚊帳干せる橋の手すりや鯊の夕 虚子
両岸の鯊釣る中に舟路かな 青邨
鯊舟の猫実川をこぎ出づる 虚子
ただし、境川の右岸左岸のどちらを歩いたかという手掛かりはない。右岸には宝城院、大蓮寺、左岸には花蔵院などの寺社があるものの、残念ながらそれらについての記述はない。
また、虚子の句に「猫実川」とあるのは、猫実川まで足を運んだのではなく、当時は境川のことを猫実川とも呼んでいたことを意味する。
3、船橋屋のこと
たけしは記す。
 『船橋屋といふ一軒の茶屋があった。其処へ一行は一先づ落付いた。茶屋と云っても海水浴場の憩み場所のやうな、ただ広い掛出しの上に茣蓙を敷いたばかりの処である。一枚の戸障子さへはまってゐない。一面の蘆原を見通して眺めはこの上もない。幸少しの風もない。浴びるやうに日が射し込んでゐる。春のやうに暖かい。』
『船橋屋といふ一軒の茶屋があった。其処へ一行は一先づ落付いた。茶屋と云っても海水浴場の憩み場所のやうな、ただ広い掛出しの上に茣蓙を敷いたばかりの処である。一枚の戸障子さへはまってゐない。一面の蘆原を見通して眺めはこの上もない。幸少しの風もない。浴びるやうに日が射し込んでゐる。春のやうに暖かい。』
汽船といい茶屋といい、この日の一行はここでも茣蓙のもてなしを受ける。
花蘆に埋もれて立つ茶店かな あふひ
ととのはぬ昼餉もどかし鯊の茶屋 立子
鯊の客どやどや入りぬ船橋屋 薊花
さて、いま私の手元に一枚の写真がある。
海水浴の海の家らしき前に六人の男女、男の子二人、女の子二人の計十人の記念撮影である。その海の家の柱には看板が掛かっていて、その薄い文字をよく見ると屋号は定かではないが、「手荷物御あづかり・・・」という文字が読める。そして、店の中には寛いでいる数人の客がいる。
写真の子どもたちばかりではなく、中央の壮年も裸足であり、また右の男性の着ている法被には、何となく「食堂」という文字が読める。いかにも海の家という感じである。
この写真は、「武蔵野探勝を歩く」を書くにあたり、浦安市議の高津和夫氏(故人)より提供していただいたものである。
氏によれば、この写真の茶屋は、「船橋屋」ではないが、船橋屋同様に当地において営業していた海の家であるという。
同じく高津議員よりいただいた昭和六年二月、すなわち虚子一行が浦安を訪ねる九ヶ月前の千葉県浦安町鳥瞰図によれば、汽船乗船場から海水浴場に向かって五つの橋が架かっており、その五つ目が江川橋であることが、左岸の花蔵院、右岸の東学院との位置関係から読み取れる。
そして、その先の海水浴場には「見はらしや」「浦浜屋 田川」という屋号の書かれた中に確かに「舟橋屋支店」「舟橋屋本店 佐藤」と書かれているのが確認できるのである。
すると、この船橋屋の位置を特定するには、江川橋から海水浴場までの距離がわかればよいことになる。
浦安市は、おそらくわが国でもっとも近代から現代へかけての変貌が大きかった街だろう。現在の浦安市の地図を眺めても旧市街地と新市街地との区分すら見分け難い。
それでも、船橋屋の所在地は少なくとも海楽一丁目ではないことは自明である。
仮に、鳥瞰図がほぼ正確であるとすれば、現在の猫実一丁目六番地周辺だと思われる。
4、吟行の参加者
最後に、吟行の参加者を可能な限り特定し、その俳句を紹介したい。
飯食ふや口にとびこむ秋の蠅 高浜虚子
(中略)
鯊舟の出はらひ居たる日和かな 山本薊花
以上、少なくとも18人である。
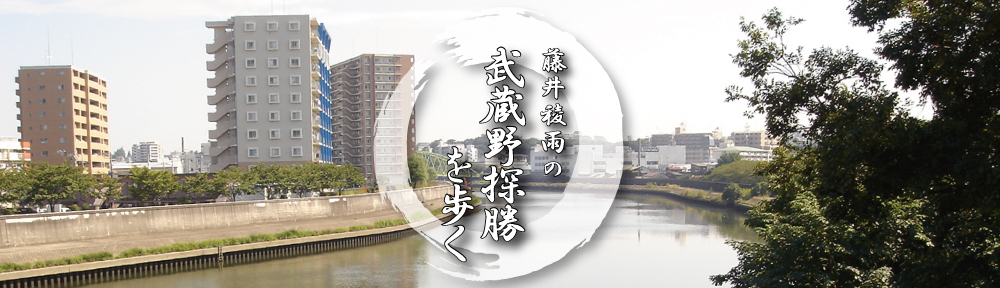
ピンバック: how to buy androxal cheap fast shipping
ピンバック: purchase enclomiphene uk delivery
ピンバック: rifaximin ONLINE FEDEX COD FREE CONSULT
ピンバック: discount xifaxan cheap from canada
ピンバック: get staxyn new zealand buy online
ピンバック: ordering avodart generic alternatives
ピンバック: discount dutasteride buy sydney
ピンバック: order flexeril cyclobenzaprine generic alternatives
ピンバック: buying fildena buy uk no prescription
ピンバック: get itraconazole lowest price viagra
ピンバック: objednejte kamagra bez lékařského předpisu
ピンバック: acheter kamagra generique
ピンバック: gabapentin no perscription no fees overnigh